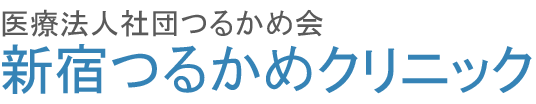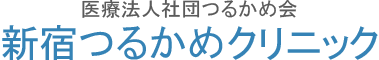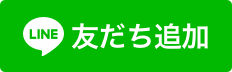ブログBlog
膵臓を食べても膵臓は治りません
消化器病センター長
田中 龍
『君の膵臓を食べたい』なんて言われた日にはちょっとしたホラーですよね。
当時、ちょうど消化器病専門医の筆記試験を控えていた私は、書店で見かけて思わず手に取りました。
一種のジャケ買いでしょうか。タイトルに持ってかれた感じですね。
内容は伏せますが、あの頃ちょっと流行った系統でしたね。
3回読みましたね。
しっかり泣きましたね、3回とも。
さて、同タイトルで一躍有名になった膵臓ですが、皆さん膵臓が身体のどの部位にあるかご存知ですか?
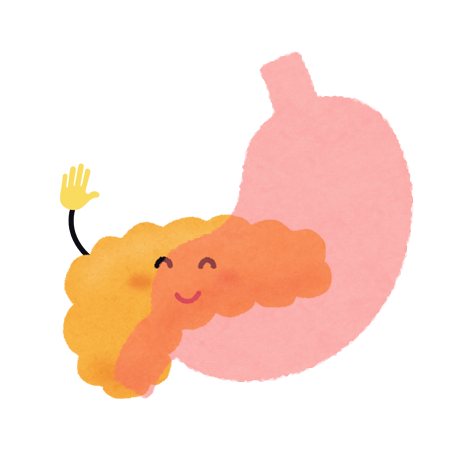
正解は胃の裏です。
お腹と背中のちょうど真ん中あたりにあります。
なので、膵臓の疾患は症状が出る場合、おなかの症状としても背中の症状としても出現することがあります。
消化器内科外来をしていると、鳩尾(心窩部)が痛くて『胃が痛いんです』って受診した方が、膵臓の疾患だったというケースは、実は少ないです。
いや、少ないんかい。
実際、心窩部の症状として来院した患者さんが膵臓の疾患だった、という頻度は低いです。
心窩部の症状はほとんど胃、食道、十二指腸など消化管の疾患や、胆石などの胆嚢の疾患です。
ただね、膵臓は怖いんです。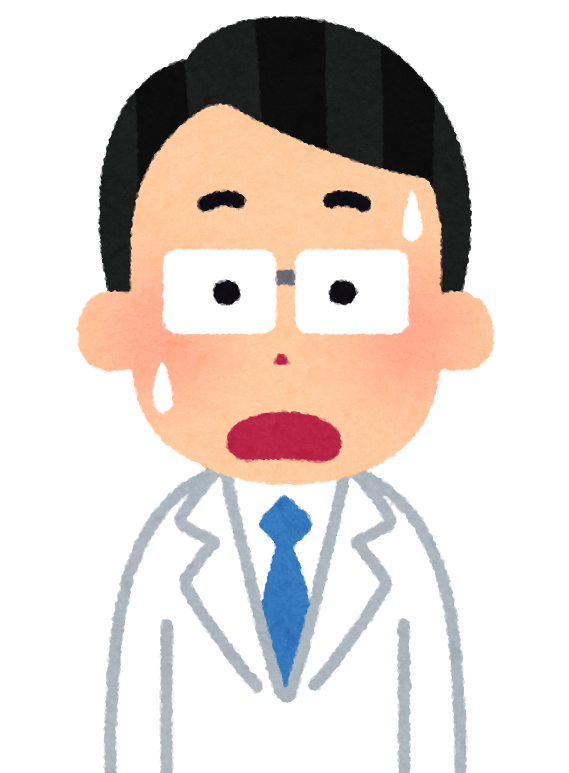
膵臓を治そうとする人に食べられちゃうんです(しつこい)。
真面目な話、膵臓の病気の代表例は腫瘍と炎症です。
実はどっちも厄介なのです。
膵腫瘍の代表例である膵がんは種々の悪性腫瘍の中でも予後が悪く、初期には自覚症状も現れにくいです。
発見されたときには進行がん、なんてことも珍しくありません。
膵臓の炎症に関しても、他の臓器の炎症と比べて予後が悪いです。
膵臓の炎症には急性と慢性がありますが、急性膵炎は時に命にかかわりますし、慢性膵炎は腹痛などの症状が長期間続くことがあります。
膵疾患はアルコール(飲酒)と深い関係があります。
ただ、『お酒飲まないから大丈夫』ではありません。
この辺りは肝臓のお話と一緒ですね。
膵腫瘍は基本的にアルコールとの関連がないものがほとんどですし、膵炎に関しても胆石性や自己免疫性などのアルコールとは関連がない原因のものもあります。
『頻度が低いなんて安心させたいのか、厄介だって怖がらせたいのかどっちなんだ!』
と思ったそこのあなた、ごもっともです。一回落ち着きましょう。

さて、では膵臓に心配があっていらした患者さんや、我々が症状から膵疾患を疑った場合、具体的にどんな検査を提案するかというお話にうつりましょう。
基本は採血と画像検査です。
前回、肝臓をスーパースターと表現しましたが、膵臓は言うなれば縁の下の力持ちです。
派手な仕事はしておりませんが、食べ物の消化を助ける外分泌機能や、色々なホルモンを分泌する内分泌機能を担当しています。(人体の中で唯一血糖値を下げるホルモンであるインシュリンも、膵臓から分泌されます。)そして肝臓と同様に我慢強いです。
採血では、この外分泌機能と内分泌機能をチェックします。
また、腫瘍マーカーで癌を示唆する所見があるかどうかをチェックすることもあります。
ただ、検査のメインは採血よりも画像検査です。
膵臓の画像検査は超音波・CT・MRI等の選択肢があり、膵臓の形態変化を見ます。
先に結論を申しあげるとCTが一番相性の良い検査になります。

少し詳しくお話をしていきましょう。
3種類の検査の中で一番ハードルの低い検査は超音波検査、いわゆるエコーです。
ただ、超音波検査は実は膵臓との相性がとても悪いんです。
理由は、膵臓の前面にある、、、そう、胃です。
胃の中の空気が超音波検査ととっても相性が悪いんですね。
なので、膵臓の全体を超音波検査で観察することは難しいです。(一部は見えます)
繰り返しになりますが、膵臓の画像検査はまずは(できれば造影剤を使った)CTで行うことが多いです。
MRIも検査として行うことがありますが、CTである程度の診断がついた後に診断精度を上げるために行う事の方が多いです。
さて、今回は膵臓に関してお話してきました。
毎回不安を煽ってしまっていますが、私が申し上げたいのは客観的に判断して正しく心配しましょうという事です。
これ、意外と難しいんです、自分の事だとなおのこと。
不安な状態って、深刻に考えすぎてしまったり、逆に楽観的に考えすぎてしまったりするんです。
1人で考え込んで視野が狭くなって凝り固まってしまう。
そんな時はプロに頼りましょう。
私は無駄な検査は決して勧めません。
気になったそこのあなた、膵臓に関して雑談しに来てくださいね。
【外来に行くなんて大事にしたくないなぁ、こっそりちょっとだけ調べられないかな】と思ったあなたは、健診の時にオプションで腫瘍マーカーを調べてみる、なんて手段もアリかもしれません。
現在、WEBでも外来予約を受け付けております↓